【 報告 】OGC シンポジウム2021・パネルディスカッション レポート
人々がつながる「デジタル共助社会」の実現に向け
地域住民と行政、企業が信頼関係を築き、共に進んでいこう!
パネルディスカッション「デジタル民主主義・DXの本質の追求」
【パネリスト】
津脇慈子 経済産業省 大臣官房企画官(デジタル戦略担当)兼 内閣官房 デジタル改革関連法案準備室 企画官
南雲岳彦 一般社団法人スマートシティ・インスティテュート理事、三菱UFJリサーチ&コンサルティング専務執行役員
末貞慶太郎 OGC理事、株式会社ブリスコラ 代表取締役
高橋範光 OGC理事、株式会社チェンジ 執行役員 New-IT Unit 兼 株式会社ディジタルグロースアカデミア 代表取締役社長
【モデレータ】
中村彰二朗 OGC代表理事、アクセンチュア・イノベーションセンター福島 センター共同統括
(敬称略・五十音順)
「日本のナショナルアジェンダをデジタライゼーションで乗り切る為に!」をテーマに開催された、「OGCシンポジウム2021」。本年はコロナ禍によってオンライン開催となったが、日本の抱える一極集中と地方産業の生産性低下など積年の問題に加え、まさにそうしたパンデミックへの対応なども含めた国家的課題をどう解決するのか。最終セッションであるパネルディスカッションでは、本格的なデジタライゼーションとイノベーションによる次の時代のビジョンをめぐって、熱気のこもった議論が交わされた。
国民目線とデータ共有によるデジタル共助社会を目指す

冒頭、各パネラーから現在のテーマや取り組みについて報告があった。現在内閣官房でデジタル庁の起ち上げに取り組んでいるという津脇氏は、デジタル庁創設に向けて、政府の側が大きく変わるべき3つのポイント=①国民目線 ②アジャイルなプロセス ③担い手・意思決定のあり方 を挙げる。
「政策を打つにあたっても、まず国が先行して決めるのではなく、国民から見て必要な施策なのかという視点から始める、いわばアプローチの変更です。また施策を決めたらできるだけ早く実施し、人々の声を聞きながらどんどん改善していく、アジャイルなプロセスに移行する。そして最後に、何ごとも行政だけで決めるのではなく、いかに民間の皆さんに参加してもらうか。意思決定のあり方そのものを変革していく必要があります」。
その実践例の一つが「デジタル改革アイデアボックス」の開設だ。
「これは国民の声に基づくデジタル政策の実現に向けた、アジャイルな政策アプローチの試みです。どなたでもユーザー登録をしていただけば、ご自身の意見を投稿でき、政府はその“国民の声”を政策に反映していけるように努力するというものです」。
すでに登録ユーザー数は5500件を超え、投稿されたアイデアは6000件以上、寄せられたコメント数は2万件以上に達しているという。
続いて発表に立った南雲氏は、現在「日本の地域発スマートシティモデル」への取り組みに注力している。一般にスマートシティと呼ばれるプロジェクトにも、企業主導、政府主導などいくつかのガバナンスモデルが存在するが、日本で求められているのは、その中間である「コミュニティ主導」型だと南雲氏は指摘する。
「地域発の分散型スマートシティを推進していくならば、やはりそこに住んでいる人たちが当事者として、協働・信頼し合っていくというモデルに育てていくべきです。進める際にも、『市民が幸せにならなくてはいけない』と明確に表明すること。つまりスマートシティの最終目的は、市民のウェルビーイングの向上にあるといえるでしょう」。
ここで重要なのは、データをもとに「地域にとっての幸せとは何か?」を定量的に示し、それを通じて地域の人々の間に、自分たちの幸せに関する合意を形成していくことだと南雲氏は強調する。国連の世界幸福度ランキング(2020年)で見ると、日本社会は個人の自由度と寛容さに欠け、さらに若い人々の社会に対する信頼度が極めて低いという。
「今は、こうした課題をデジタルで解決していく恰好のチャンスです。具体的かつ明確な数字を示すことで情報の透明性を確保し、そこから市民同士の信頼を育て、より自由で寛容な社会を創る。いわば、日本の共助のデジタル化ができないかと考えています」。
デジタルの便利さを伝え、オープンAPIでそれを実感させる
デジタル人材育成に取り組んでいる高橋氏は、「今、高度人材だけでなく、より広くデジタルを使える人材の育成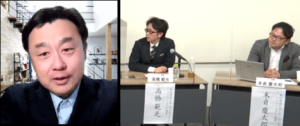 が求められている」と説明する。これまでも、高度 IT 人材の育成は喫緊の課題とされてきた。だがDX が社会に浸透していけば、さらに高度なサービスを理解し、世の中の人々に広く活用してもらうための「仲介役」が必要になるというのだ。
が求められている」と説明する。これまでも、高度 IT 人材の育成は喫緊の課題とされてきた。だがDX が社会に浸透していけば、さらに高度なサービスを理解し、世の中の人々に広く活用してもらうための「仲介役」が必要になるというのだ。
「スーパーシティ/スマートシティの推進で、私たちベンダー側が高度な議論を交わしていても、肝心の現場で業務を行う自治体職員が取り残されている状況では、せっかくサービスやツールが導入されても、誰も使わないということになりかねません」。
そこで高橋氏は、「デジタルを使うメリットを人々に理解してもらうためのスキルやリテラシーを備えた人が必要になる」と指摘する。たとえば新型コロナの給付金なども、もっとマイナンバーカードが普及していたら、給付がスピードアップできただろう。
「デジタルを使えば給付金が早くもらえる=自分たちにメリットがあるという理解を通じて、未知のものへの抵抗感を払拭する。そうしたデジタルリテラシーを社会に育てること。さらにそのための『仲介役』人材を育てることが、今後は重要になってきます」。
一方、末貞氏は技術者の視点から、「オープンイノベーションのキーとなるのは、オープン API」だと提言する。自身、現在スーパーシティのプロジェクトに参画している経験からも、API の標準化により現場側を意識した、共通化をベースとした都市OSの重要性には大いに着目しているという。
「標準化が実現すると業務の現場の自由度が飛躍的に高まりますが、その標準化を実現するための技術がAPIです。API の標準化は、大きく①インターフェース②プラットフォーム ③開発手法の3つに分けられ、このすべてがそろうことでスーパーシティのガバナンスが実現可能になります」。
具体的なプロジェクトで言えば、①行政がインターフェース仕様の標準化を行い ②データ連携基盤整備事業者がプラットフォーム標準化を進め ③先端的サービス事業者が開発手法の標準化を実現して、最終的に自治体=スーパーシティにおける情報活用のガバナンスを構成するという構図になる。
「こういうスーパーシティのデータ連携基盤が構築できれば、その後は自治体の担当者はキラーサービスを作ることだけに注力すればよくなります。そのために、行政の現場から期待される技術やサービスを提供していくのがIT 業界の使命だと考えています」
自分自身、ひとりの住民として課題を見直してみるのが大事
パネルディスカッションの冒頭で中村氏は、4名のパネラーの発表の中に、今回のシンポジウムのテーマでもある「地域の人々とのフラットな関係づくり」や「デジタル活用による地方創生」の大前提となるキーワードがあったと指摘した。
「発表の中で『国民目線』という言葉がありましたが、地方創生に取り組む際には、市長でも企業経営者でも、まず自分がひとりの市民だという視点が大切です。お互いに市民の立場で人々と話をして、そこでできあがった施策を実行する時には、それぞれの役職で頑張るという順番がとても大事なのです」。
そのために市民の側も行政任せではなく、各人が地方創生の課題を「自分ごと」と捉えてもらう必要がある。それにはどうしたらよいのだろうか。津脇氏は、「困っているのは国民だけではなく、自治体や政府の職員も1人のデジタルサービスのユーザーとして、自分たちの課題に目を向ける必要があるのではないか」と言う。
「以前キャッシュレス化を担当していた時に、電子マネーなら全国どこでも使えると思っていたが、地方に実際に足を運んでみて、むしろ使えないケースも多くあると知りました。このとき、実際に現地に行く、現場の声を聞くことが、非常に重要だと感じました」。
また南雲氏は、「地域の自分の確立」の大切さを、みずからの経験に基づいて語る。
「私の世代は猛烈サラリーマンが多いので、会社のことしかわからないという人も少なくありません。それが、たとえば自分の子供の運動会などを経験するにつれて、地域で生きているという感覚を実感できるようになる。私の場合はそうした体験を通じて、地域の自分を確立していったのが、『自分ごと』の感覚を持つ良い契機になりました」。
特に現代は、社会に出ると会社などタテ社会の肩書きなどが人々を隔てる壁になりがちだ。それを超えてお互いに意見を言える基盤を作るのが、地域社会でのトラスト=信頼関係作りの基本になると南雲氏は語る。
2021年をデジタル元年として共に力強く進んでいこう
高橋氏は「自分ごと」意識を醸成する上で、2つの重要ポイントがあると指摘する。1つは「議論の前にメリットを明確に訴求すること」だ。たとえばスーパーシティ構想を進めるにも、アーキテクトが住民を説得するというアプローチではうまくいかない。市民1人ひとりの目線に立って、それがどんな良いことをもたらすかを説明し、市民自身に「参加した方が良い」と腹落ちしてもらうのが大事だという。
「もう一つは、将来の地域を考えた時に、将来の世代の利益を代表する役割を意識できる人が議論に加わることです。その場のメンバーがもういない30年後とか50年後に、ちゃんと次の世代にメリットを残せるのか。そういう意識を持った上でビジョンを話し合うのが、スーパーシティなどでは非常に重要です」。
末貞氏は、コロナ禍にあって、あえてフェイストゥフェイスの場づくりの重要性を説く。
「最近はなかなか社員を会社に集めて話す機会がなかったのですが、感染の勢いが弱まった時期を見計らって対面で会議を持ったところ、Webで議論するよりも生産性が10倍くらい向上しました。これはスーパーシティ計画などでも大事で、最初にメンバーの目的を共有するコミュニケーションとしては、こうした“場”をどう作るかが重要だと再認識しました」。
この最初の意識共有ができれば、そのあとの Web を通じたコミュニケーションも格段に質が向上すると末貞氏は言う。
ディスカッションの終盤、中村氏は改めて「人間中心の地域 DX」の実現には、デジタルを活用した双方向コミュニケーションが重要であり、それにはやはり「すべての課題は自分にある=自分ごとの意識醸成」が最重要のテーマだと総括する。
「自分のために、あるいは地域や次世代のためにやっていこうという意識を持てれば、お互いの間に信頼関係が築かれ、非常にポジティブな社会に向かいます。私が長年担当してきた『スマートシティ 会津若松』でも、今まさにそうしたゴールに向けて動き出しているところです」。
最後に中村氏は、2021年こそはデジタル元年を成功させるために立ち上がる時であり、その重要な契機となるデジタル庁創設の成功に向けて、官民ともに力を合わせて進んでいこうと力強く呼びかけ、パネルディスカッションを締めくくった。
(ライター・工藤 淳)




































